| 李 容淑 著 の"甘口辛口″目線文化比較論さくらとキムチに掲載されました。 |
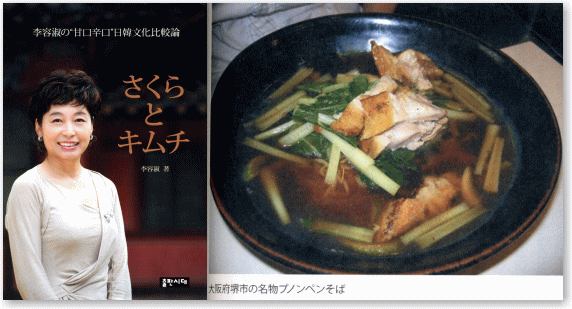 |
内容は・・・・神様がつくったらーめん<プノンペン> 達磨さんのような人だった。頭は丸坊主、鼻からは下はひげで覆われていて、お腹は太鼓腹で布袋(ほてい)さんを連想させる。目はギョロッとしており、話し方はぶっきらぼうで、およそお客さんに対する丁寧な言葉遣いではなかった。 私が日本の大阪に来て家を持ったのは三人の子供たちの通う学校に近い場所で、近所には韓国人は殆ど住んでいなかった。そこは、日本武家屋が多く集まっているところで、日本食レストランと洋風のファミレスが国道沿いに競うように立ち並んでいた。 週末や休日になれば子供たちと車で郊外に出かけ、動物園に行ったり、地区の運動会に参加したりして過ごした。 そのような時には、帰宅する途中で評判の飲食店に立ち寄り、珍しい日本食を食べるのが何よりの楽しみだった。 ところが、時が過ぎ、そのような外食の機会を重ねるに従い、お腹一杯食べても何故か胸の片隅には物足りなさというか釈然としない気持ちが湧き上がって来るようになった。それは言葉で言い表せないジーンとした郷愁のようなものだった。日本に来たころは異国の地に適応するのに必死で、食べ物に対する懐かしさを感じる余裕も無かったが、生活に慣れてくると徐々に祖国の食べ物が恋しくなって来た。母親が作ってくれた好物の料理を好きなだけ食べて得られるあの満足感、異国の食べ物ではけっして感じられないあのなつかしさ、そういったものに対する郷愁が一度に押し寄せて来たのである。 秋風がしとしと降り注ぐ日だった。その日は、会社でもいつになくストレスが多く続いた。そこで、普段より早く仕事を切り上げて会社を出た。川岸に沿って歩いていると、ふと私の目に触れる店があった。人々が前で列を作って待っているその店は一般の家庭のようで、小さい食堂のようにも見えた。近づいてみると、入り口に垂れ下がっている暖簾は「プノンペン」となっていた。プノンペンと言えば、間違いなくカンボジアの首都ではないか。ここは一体、何を売る店で、こんなにも多くの人々が並んでいるのだろう? 突然、好奇心が沸き起こり、店の中を覗いてみた。ガラス窓のむこうでは数人のお客さんが麺のようなものを食べていた。なんのことはない、ここはラーメン屋だったのだ。私は入り口のドアのところでソワソワしていたが、立派な口ひげを蓄え、ツルツル頭のおじさんは私を無視したように、特別な反応を示さなかった。 日本ではお客さんの姿が見えると、店の主人は大声で、「ハイ、いらっしゃい!」と大声で威勢よく迎えるのが普通だが、このおじさんはジロリと一瞥を与えただけだった。その無愛想さは私が日本に来てから初めて経験するもので、けっして心地のいいものではなかった。それなのに、店の中に漂う匂いは何故か私の心を捉えた。それに、こんなに大勢の人が列を作って混み合うのを見て一度試してみたくなったのだ。とにかく列に並んで私の順番が来るのを待つことにした。 「一人か?」 初めておじさんが私に声をかけて来た。それも怒ったような大声で。なにか一人で来たことが罪でも作ったような気分になり、私は声も出せずに頷くだけだった。すると、おじさんはカウンターの一番隅っこを指し示し、そこに座れととの信号を送ってきた。私はそれに従い、黙って静かに座った。ところが、いつまで待っても誰も注文を取りに来ないし、水ももって来てくれない。 「あのー、ここにラーメンひとつください」 私は蚊の鳴くような声で言った。 「ここはラーメンなんか食わせない。誰がラーメンて言ったんだ。ソバなんだ。ソバ!」 私は叱り飛ばされた感じだった。ふとそのとき、韓国の食堂でも客を客とも思わない口の悪いアジュマ(おばさん)がいたことを思い出した。 「ハイ、申し訳ありません。ソバひとつください。それとお水一杯ください」 「水は自分で取りに行くんだよ」 とおじさんはあごを突き出して水のあるコーナーを教えてくれた。そうなんだ、水はセルフサービスなんだ。そうして待っているうちに、ようやく一杯のソバが私の前に置かれた。 雨が降り、会社でもいやなことがあり、気分転換に入ったラーメン屋では無愛想なひげ面のおじさんに叱られるし・・・。キムチもつかないソバ一杯こっきりを前にした私は侘しい気持ちを抑えきれなかった。まるで無人島にいるような孤独を感じた。 ところが、ラーメン、いや、そうじゃなかった、ソバだった、そのソバを少しだけでも食べて元気を出そうと思い、一口、スプーンで汁を口に入れた。 その瞬間だった。 「美味しいっ!。ラーメン、いや、ソバでこんなに美味しい味が出るのかしら!」 自分の口が信じられないほど美味しかった。そして、また一口、また一口・・・。 その時、不意に母の顔が浮かんだ。そして、祖母の顔、それから韓国に残っている兄弟達の顔、懐かしいものすべてのものが走馬灯のように次から次へと頭の中を通り過ぎていった。長い間あっていなかった人たちと再会した時の喜び、興奮、スリル、満足感など万感が胸に迫って来て、思いもよらなかったことだが、二スプーンのソバ汁で涙が滲み出てきたのだ。 <どうしてソバの一杯が私をこんなに泣かせるのだろう?> 私は息もつかないでソバの器に吸い込まれて行った。その間、涙、鼻水、汗のしづく等々、すべての懐かしさの想い出が溢れだした。 ソバの中には、私たち韓国でいつもキムチや野菜を一緒に食べるように、細かく刻まれたチンゲン菜が一握り入っている。そのさくさくとした食感がなんとも言えず、歯ごたえのある麺と相乗効果を出している。いつの間にかこの日、滓のように溜まっていたモヤモヤした気分はすっかり晴れ上がっていた。その上、ついさっきまで感じていた孤独感もピリ辛スープのお陰できれいさっぱりと解消されていた。 ここで、プノンペン・ソバの特徴を簡単に紹介しておきたい。 まず、一人ひとりの客から注文を受けて初めて新しいスープを作る。最初、水の中にこの店独自に開発したスープをの原料を入れ、そこにニンニク、料理用清酒、セロリ、トマト、豚肉数切れ、唐辛子の粉と種、塩などを入れてスープを作る。麺は別に沸かしているお湯でゆで、それを取り出して器に入れる。そして、その上から別に作っておいたスープを上から注ぐ。 このように、客が来て初めて作るから多少時間がかかるのはやむを得ないが、スープが一般的な骨汁ではなく、ピリピリした味付けの野菜汁なので大好評なのだ。 ラーメン一杯で大満足したという経験はこのときが初めてで、この後、私がこの店をどれくらい愛用してきたかは創造していただけるだろう。 あれから二十年近くが経つ。初めて訪れたときとは目もあわせてくれなかった怖いおじさんと無愛想なおばさんも、今や私が入り口のドアを開けると、 「あ、李さん、いらっしゃい。久しぶりだね。今年はなかなか来てくれなかったので、どうしてるのかと思っていたんだよ」 と言いながら、とても嬉しそうに迎えてくれる。以前は子供たちと一緒に翌来たものだったが、今では子供たちも独立し、離れ離れの生活を送っているので、家族揃ってくることはもう無い。それでも、息子や娘が別々に大阪に来たときは必ず一緒に来るようにしている。それは、私たち家族の過去の思い出と郷愁に出会うためとも言える。 そのような時、私たちは必ず韓国の海苔やキムチをお土産に持って行く。 |